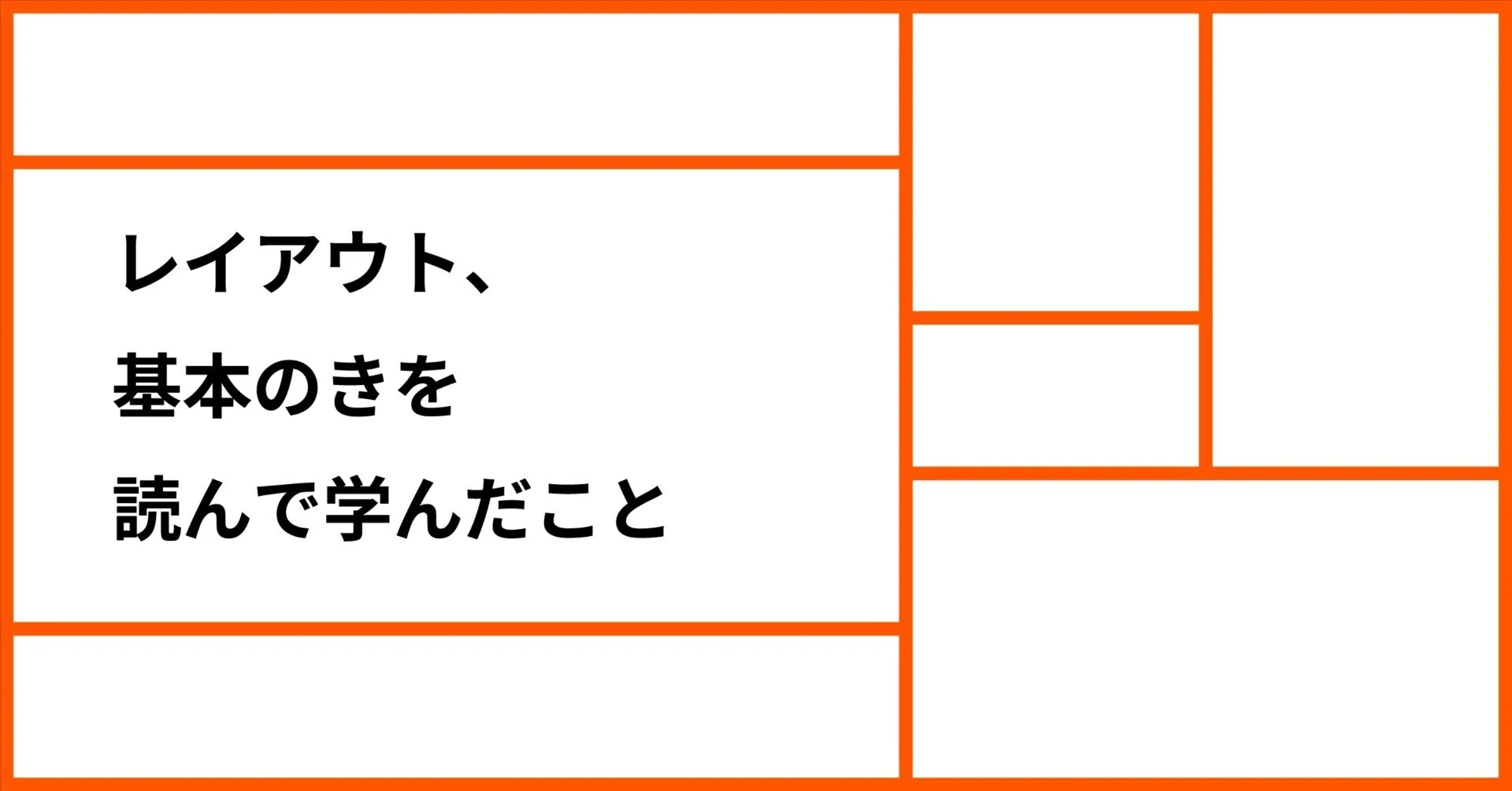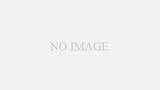rirumaruです。
レイアウト、基本の「き」という本を読んでみました。グラフィックデザイナー歴が浅く、デザインに時間がかかってしまう人に是非読んでほしいです。レイアウトだけではなく、デザインの基礎など学べることがたくさんありました。文字や写真などの扱い方や配置することでどういった印象や意味をもたらすのか知りたい人におすすめです。
まえがき
デザイナー歴2年の私。デザインをするときに、どんなレイアウトにするのかよく迷います。レイアウトの基礎を学べば、素材や文字量、伝えるべき情報を素早く配置できるようになり、デザインの完成速度も上がるはず。そう思い、この本を手に取りました。
レイアウトを意識する
普段デザインを見ていて、どんなところを見ていますか?
かっこいいや可愛いだけで終わるのは勿体無いです。ただ見るのではなく、デザインの要素を意識してみることが大切です。なぜ、意識することが大切なのかというと、上下中央は必ずしも中央に見えるとは限らないからです。
例えば、よく見るYouTubeのロゴ。赤い長方形の中に右向きの三角形が中央に配置されていますが、実際には3mmずれています。このように上下中央は錯視によって、人間の目では上下中央に見えないからです。
レイアウトを意識的に見ることで、なぜ情報がわかりやすく入ってくるのか?なぜこのレイアウトは読みやすいのか、理解することができます。
全体構成を考える
私が一番知りたかった内容が記載されていました。デザインを考える上で大切なこと。それは全体構成を考えることだと感じています。全体の構成を決めてしまえば、作業も取り組みやすくなります。
まず、読みづらいレイアウトとはどういったものだろう?
余白が詰まりすぎている。文字サイズがおかしい。コントラスト…などなど
それらもありますが、この本では、目の流れが大切だと書かれています。目の流れとは、文字を読むときに流れる視線のことです。
例えば、小説の場合、基本的に縦組みで構成されているので、スラスラと読み進めることができます。また、視線誘導には3つの型があります。F型、N型、Z型。
F型
左から右へ、左下を繰り返す形。
教科書やニュースサイトやブログなどに見られるレイアウトです。
文字が多いものなど、読んでもらうことをメインするときに使います。
Z型
Z型は、左から右へ視線が流れ、次に左下へと移動する形。F型と似ていますが、F型は全体のレイアウト、Z型は一つのブロック単位で考えると分かりやすいです。
N型
N型は、上から下へ、左上を繰り返す形。
雑誌や書籍に見られるレイアウトです。
写真との組み合わせで使用したり、和テイストのデザインに使えます。
そういえば、お品書きもN型レイアウトをよく見ます。
これらを意識して作るとユーザーが読みやすいレイアウトを作成することができます。
自分なりの解釈
正直言うとまだレイアウトに迷います。
上記のレイアウトはあくまで基準であり、写真、文字量、コンセプトによってレイアウトはいくらでも変わるからです。
結局のところ、読者やユーザーにとって最も伝わりやすい方法を考え、それに合ったレイアウトを選ぶのがベストだと感じました。
他にも、図やグラフなどの作り方や色の選び方が解説されていて、学ぶことが多かったです。
最後に
この書籍は、特にグラフィックデザイン初心者におすすめしたい一冊でした。
最後まで読んでいただきありがとうございました。